●木材腐朽の三要素と湿気のコントロール
木材が腐るには「水分・温度・空気」の三要素がすべて揃う必要があります。 腐朽菌の種類などによっても違うので、厳密にはいえませんが、腐朽が進みやすい環境条件は
- 湿度80パーセント以上、木材の含水率20パーセント以上
- 気温 20度~30度
- 酸素がある
という環境です。 この条件の内、気温と酸素についてはコントロールすることができないので、湿度のコントロールが最も重要になります。
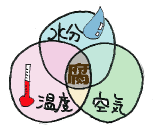
(挿絵:店長くり坊)
木材が腐るには「水分・温度・空気」の三要素がすべて揃う必要があります。 腐朽菌の種類などによっても違うので、厳密にはいえませんが、腐朽が進みやすい環境条件は
という環境です。 この条件の内、気温と酸素についてはコントロールすることができないので、湿度のコントロールが最も重要になります。
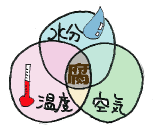
木材は周囲の環境にあわせて常に水分を吸ったり吐いたりしています。 水分を吸えば膨張し、吐けば収縮します。 例えば鉄やプラスチックが熱によって膨張収縮するのに似ていますが、決定的に違うのは、収縮の仕方が均一でないという点です。
といった問題があり、これは木材の長所になることもありますが、扱いにくさの大きな要因になっています。結果として、「反り」「割れ」「隙」といった現象がでてきます。
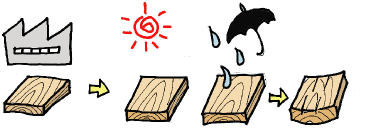
特に、屋外の場合は、常に日光の直射、風雨、昼夜の寒暖の差にさらされるため、
屋内の使用環境と比べて想像以上に過酷です。ちょうど、裸のまま屋外で1年を過ごすことをイメージしていただくと、
その過酷さが想像いただけるでしょう。屋内ではあまり気にならない木の割れや反りも、屋外では当たり前に発生します。
紫外線の影響で、木材表面の組織が破壊される現象が「日焼け」です。
新しい状態では、赤味を帯びた木の色が一般的ですが、紫外線で木の組織が破壊されるとともに、灰色に変色してきます。
最終的には銀白色にはり、表面が脆くなりますが、紫外線は木材の内部までは到達しないので、材の組織が破壊されるのは表層だけです。
そのため、日焼けそのものが木材の強度低下に直結するわけではありません。
ただし、破壊された層は水分も浸透しやすく、湿度の高い状況になると、表層が腐朽に適した湿度を保持しやすくなります。
木を紫外線や風雨から守るために施されるのが屋外用塗装です。
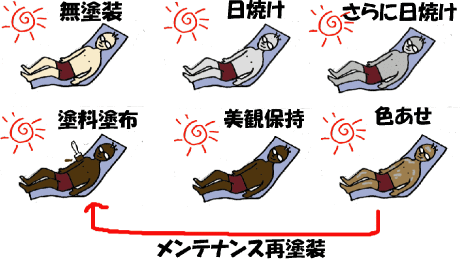
木材の表面に塗布される屋外用の塗料は、紫外線をカットする効果と、木材内部への水分の浸入を抑制する効果があります。
しかし、紫外線や雨、あるいは磨耗の影響でだんだんと色あせや、塗装の部分的な落ちが発生してきます。
そのため、木材を保護する効果が低下してきますので、定期的な再塗装を行なって、美観と効果の保持を行なう必要があります。
プランターの中には直接土を入れますし、毎日水遣りをすれば当然濡れます。
梅雨時には乾く間もないかもしれません。屋外に使う木製品の場合には、ある程度折込済の条件ですので、極端に神経質になる必要はありませんが、できることだけはしっかりと対処しておきましょう。
それによって、使用できる期間に数倍の差が生まれます。
木製品を長持ちさせる最大のポイントは「湿気のカット」ポイントは、
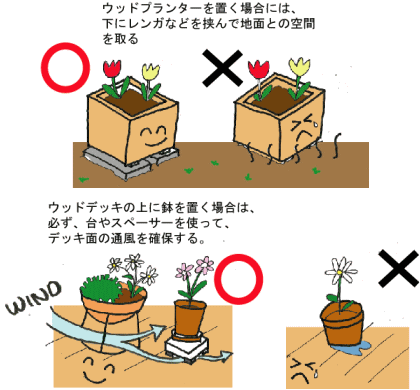
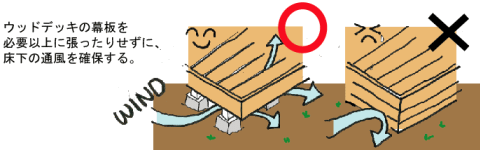
地面は湿気の最大の供給源であるとともに、腐朽菌やシロアリなどの木材の劣化を促進させる生き物の生活圏です。
地面と木材が接していると、そこから水分が無限に供給されるので、木材の腐朽条件が揃いやすく、そこに腐朽菌やシロアリなどが入り込んで腐朽、劣化を加速させてしまいます。
地面との距離をとることで、湿気と腐朽菌とシロアリの経路を遮断することが重要です。
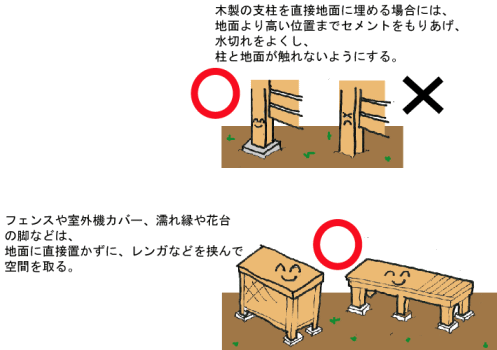
塗装が部分的に落ちてムラになってくると、著しく美観が低下してきます。
そのまま放置すると、紫外線による劣化が進んで、再塗装しても色むらが目立つようになります。
再塗装をしないからといって、極端に木材の腐朽が進むわけではありませんが、美観を保持し、より長く使うためには必要な作業です。
再塗装のサイクルは、使用される場所によって大きく変わってきます。 塗装劣化の主な要因は、「日当たりの良し悪し」「雨のかかり具合」「歩行などによる磨耗」です。
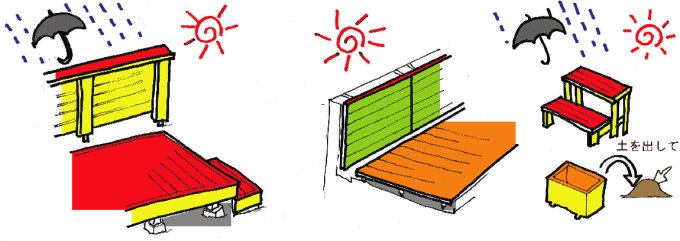

水平面・ひさしなし → 1年に1回程度

水平面・ひさしあり → 2年に1回程度

垂直面・日あたり普通 → 3年に1回程度

垂直面・日あたり悪い → 4~5年に1回程度

日当たりなし・雨かからず → 再塗装しなくてもよい
長い目で見たとき、第1回目の再塗装のタイミングが重要です。 工場で塗装した際は、木材の表面が劣化していないので、塗料も深くは染み込んでいません。 屋外でしばらく使用すると、木材の収縮による細かな割れが出てくるとともに、紫外線などの影響で表面が劣化してきます。 塗装の色褪せがあまり目立たず、表面が少し劣化しかかったタイミングが1回目の再塗装に最適なタイミングです。 タイミングとしては、概ね、適切な再塗装の間隔の半分が目安になります。ウッドデッキであれば、半年程度。 フェンスであれば1年半程度です。このタイミングで塗装しておきますと、塗装がムラになりにくく、 ある程度塗料も深く浸透しやすいので、2回目以降の再塗装の時期が長くなります。
再塗装は、純正の塗料をご利用いただく必要はありませんが、必ず屋外用のステイン塗料をご利用ください。
ペンキのような造膜型の塗料の場合には、木材内部に入った水分が抜けにくくなるため、腐朽を早める恐れがあります。
再塗装の留意点
塗料には、大きく分けて
「水性塗料⇔油性塗料」
「含浸型塗料⇔造膜型塗料」
「屋外用塗料⇔屋内用塗料」
といった区別があります。それぞれ、特徴的な違いがありますので、解説してみましょう。
| 水性塗料 | 油性塗料 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 顔料などの成分をを「水」に混ぜて塗料としたもので、原則的には、水分の蒸発によって定着し、刺激臭はほとんどありません。 また、完全硬化後は水にも流れません。 |
顔料などの最終的に定着する成分を乾性油に混ぜて塗料としたもの。自然塗料などもこの分類に入るが、一般的にはシンナーを薄め液に使用するため、刺激臭が強い。 | |
| 長所 | 刺激臭もなく、有害物質の揮発もないので、安全性が高く、扱いやすい。 特に、再塗装などでは、近所迷惑にならない。 |
油性であるため、木材表面が毛羽立ちにくく、また着色の場合も透明感があり、下地の木目を生かしやすい。 | |
| 短所 | 水性であるため、毛羽立ちやすく、また、塗装はべたっとした感じになりやすい。 | 刺激臭があり、有害物質を揮発するものもあるため、換気を十分にする必要がある。 再塗装では、近所への迷惑になる場合もあり、シンナーも必要であるため、扱いにくい。 |
|
| まとめ | 仕上がり感は油性の方が優れているので、工場内での塗装の場合いは、今でも油性が多く使われるが、健康や安全を重視する近年の動きから、水性塗料の割合は年々増加している。 | ||
| 含浸型塗料 | 造膜型塗料 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 木材に浸透して定着する塗料で、一般にステインと呼ばれる。染み込んで色は付いているものの、表面には膜を作らないので、木材は無塗装の状態に近い状態で湿気の放出、吸収を行なっている。 | 表面にしっかりとした塗装の膜を作るタイプで、ウレタンニスや、ペンキなどが一般的。 木目が隠蔽されているので、掃除が簡単で、湿気の放出も抑えられるので、木も反りにくくなる。 |
|
| 長所 | 木材が湿気の吸収、放出を行なえるので、湿気がこもりにくく、屋外には適している。 再塗装の際には、洗浄後、そのまま塗装しても問題ない。 |
表面に平滑な膜を作るため、掃除がしやすく、含浸型にくらべると磨耗にも強い。 | |
| 短所 | 表面に強い膜がないので、磨耗に弱く、ウッドデッキなどのよく歩く部分の塗装が取れやすい。木材表面の細かな穴も残っているので、汚れがつきやすく、屋内では掃除が難しい。 | 屋外に使用すると、紫外線や水によるクラックや剥離が発生する。屋内でも、窓際など、結露や紫外線の影響を受けやすい部分の床表面の塗装が劣化しやすいのもこのためである。 塗装が劣化した場合の再塗装は、塗装を完全に落としてから行なう必要がある。 |
|
| まとめ | 屋外であっても、金属などではペンキで塗装することが一般的であり、造膜型のペンキそのものが屋外に適していないわけではない。ただし、木材の場合には、収縮による割れが発生するため、その割れから入った水分が木材表面のペンキの膜によって閉じ込められ、結果として、木材の含水率を高め、木材の腐朽を促進してしまう可能性がある。また、再塗装も容易でないので、屋外には含浸型の方が無難である。 | ||
| 屋外用塗料 | 屋内用塗料 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 紫外線カットの観点から、通常色つきで、湿気を木材に閉じ込めないように、含浸型が一般的。 | 屋内の仕上げに使われる塗料で、色を付ける「ステイン塗料(含浸型)」や、表面に透明の膜を作るウレタン塗料、ペンキなどがある。 | |
| まとめ | 屋内用を屋外に使えば、短期間で色あせたり、ひび割れたりするため、使えない。 一方、屋外用の塗料は屋内でも使用できるが、そのままでは、表面に塗膜がないので、木目に埃が溜まったりしやすい。 |
||
| 水性含浸型塗料 | 水性造膜型塗料 | |
|---|---|---|
| エクステリア商品 プランター フェンス デッキ材 濡れ縁 など |
ガードラックアクア(和信化学) GENGEN エクステ エナメル ガーデニング商品全般 ※MB、DB、NL、WB、GG、CB ※OLD ASHIBA灰白、灰緑、炭黒 ≫メンテナンス用塗料のご購入 |
|
| OLD ASHIBA商品 フリー板 ラック 家具類 小物 など |
ガードラックラテックス(和信化学) OLD ASHIBA薄茶、鶯茶、濃茶 ≫メンテナンス用塗料のご購入 |
GENGEN eLF 木部内装用 マット ※OLD ASHIBA商品全般 屋内用上塗りに使用 |
使用条件の厳しい屋外用に比べて、屋内用の場合には、塗料についても幅広い選択が可能です。
無塗装をご購入いただき、お好みに合わせて塗装するのもオススメです!
ワックス、オイルともに、表面に強い膜を作らないので、メンテナンスしやすいのも魅力です。
どちらか一方だけの塗装でも使用できますが、オイルを塗布してから、
ワックス仕上げをすることで、表面を保護する効果をアップできます。
※ワックスやオイルは、表面に強固な塗装膜を形成するわけではないため、
濡れたコップを長時間置けば丸い跡が残ったり、磨耗により下地が出たりする場合もあります。
これは欠点でもありますが、そういう場合でも再度オイルやワックスを塗布することで容易に修復できるのも特徴です。
また、服や雑巾で強く擦ると、色などの成分が付着する場合があります。
さらに、滑りやすいもの、滑りにくいものなどの商品による特徴もありますので、用途にあわせて検討してください。
再塗装の方法は商品によっても多少違いますが、ウッドデッキを例にとって、手順をご説明します。
再塗装に使う塗料は、必ずしも当店で販売するものでなくてもOKですが、
を確認してください。表面の撥水効果が残っている場合は、色むらや定着不良の原因となりますので、 表面を軽くサンディングするなどの処置が必要になります。塗料の完全乾燥までには1日程度かかりますので、 乾く前に濡れると塗料が落ちる場合があります。天気予報を確認してから塗装作業に入りましょう。
塗装する面についた汚れや埃、砂などを落とします。
水で洗い流しながらやわらかめのタワシなどを利用してもOKです。
(擦りすぎると塗装が落ちてムラになるので注意)
掃除の際に水洗いした場合には、しっかりと塗装する面を乾かします。
濡れた状態では、塗料は浸透しにくかったり、ムラになったりします。
塗装面から近い壁や、色を着けたくない金具などは、マスキングテープなどをつかって、しっかりガードしておきましょう。
メンテナンス用塗料(原液)は、しっかりと攪拌してから水で倍に希釈して塗装してください。
一度希釈すると、長期の保存はできなくなりますので、使う分だけ希釈するのがポイントです。
希釈率を低くすることで「濃く」することもできますが、木目が見えなくなったり、塗装のムラが出やすくなったりしますのでご注意ください。
倒れにくい安定した容器を使ってください。牛乳パックを半分の高さにカットしたものでも代用できます。
紙コップなどを利用して、希釈のための計量用カップを作っておくと便利です。
※OLD ASHIBA用塗料(灰白、灰緑、炭黒を除く)の場合は、希釈せずに使用してください。
塗装はハケで行ないます。最初からメインの場所から塗ると失敗しやすいので、まずは、目立たない場所で試し塗りしてから問題のないことを確認して全面を塗装しましょう。
木目に添って、肩幅の倍くらいの距離を目安に、手首の返しを使って塗装します。
同じ場所を2~3回なでるように往復し、できるだけムラにならないようにします。
スムーズに横移動しながら、塗装が乾かないうちに1枚の板を塗装し終わるようにします。
塗装後1時間~3時間程度で手で触っても塗料がつかない程度に乾燥してきます。
このくらいになれば少しくらいは歩いても大丈夫です。
ただし、完全乾燥までは丸1日程度かかりますので、それまでは水に濡れしたり、重いものを乗せるのは避けてください。
残った塗料の内、原液については長期の保存ができますので、そのまま保存しておきましょう。
希釈済の塗料は新聞紙やティッシュなどの染み込ませて燃えるゴミとして処分してください。
ハケなどは水洗いして保管してください。